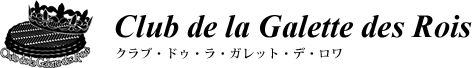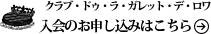柳 正司(パティスリー タダシ ヤナギ)2015年07月30日
ピュイ・ダムールPuits d’amour
ピュイ・ダムール、久しぶりに作りましたよ。実にシンプルですが、表面のカラメルの焦げ味が生地の香ばしさと響き合って全体のバランスが取れているあたり、やはり伝統的なお菓子の力を感じますね。
パティシエとして最初に務めた三笠会館から、調布にあるピュイ・ダムールというお菓子屋さんに移ったのは70年代半ばのことです。店主はフランス修行を積んだ人、お店に並んでいたのはバタークリームをたっぷりと使い、甘さもお酒もしっかり、という強烈にフランスを感じさせるお菓子でした。フランス語の製菓用語、アーモンドを自ら挽いてパウダーにしたり、ピスキュイが持てないくらいしっかりとアンビベするなどの作業、仕事の全てが新鮮で、「これがフランス菓子か」と夢中で吸収していました。ちょうど島田さんや河田さんたちがフランスから帰ってきて、本場のお菓子を展開していた頃。自分もあんなお菓子を作ってみたいなぁと、それは憧れたものです。
店名にもなっていたピュイ・ダムールというお菓子もここで知ったもののひとつです。小さなセルクルの一つ一つにジェノワーズやクリーム、ムースを重ねてきっちりと組み立てるものが主流と思っていた当時の自分に、「焼いて詰めただけ」のこのお菓子は拍子抜けするほどシンプルに映りました。それがなぜか印象的だったのは、流行とはまるで無関係のこのお菓子に、物言わぬ迫力のようなものを感じたからかもしれません。
その後クレッセントのシェフ・パティシエとしてレストラン・デザートを中心としたお菓子を手がけるようになりました。月替わりのメニューの中で、しっかりとした食事の後のデザートとして食べ口は軽く、でも素材の味を生かした印象に残る一皿を、と課題は多かったですね。その中で、コンスタントに「自分のお菓子の味」を出せるようにと研究を重ねました。糖度やPH値を計る機械などもなかったですが、実験のように試作する中で自分の勘が養われたのだと思います。
今でもそんな感覚は抜けていません。自分の求める味のイメージは決まっていても、素材の状態は流動的。常に複数の作り方を試して比較し、全体のバランスを見て調整しています。理想に近づける作業は、フランス菓子に開眼し、その味わいを一途に求めていた頃の気持ちに通じるのかもしれませんね。